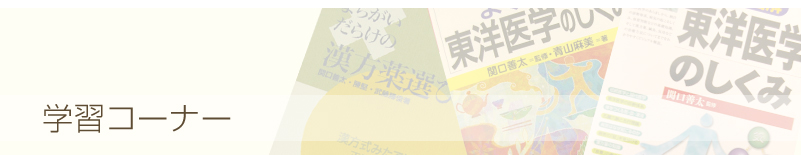学習コーナー
内科系の漢方薬治療 [漢方薬の知識]
胃痛・腹痛の漢方薬治療
各証タイプに対応した漢方薬については、日本で製品化されているものを中心に紹介しますので、中国などで煎じ薬として処方されるものとは異なる部分があります。
寒邪タイプ:
天候や冷房による外寒性のものには、「香蘇散」や「麻黄附子細辛湯」、「桂枝加苓朮附湯」
を用います。冷たいもの飲食などによる内寒性の場合には、「呉茱萸湯」などを用います。痛みが強いものに対しては、中国では「良附湯」を用いるのですが、日本にはない処方です。しかしこの処方は、良姜と香附子という2種類の生薬でできていますので、この2種類の生薬を買って煎じることで対応できます。
肝鬱タイプ:
市販では、本来の「柴胡疏肝散」を用いるのですが、医療用にはないので、処方箋で服用したい場合は、少々効果は落ちますが「四逆散」で代用します。慢性化して肝脾不調になった場合には、四逆散を「四君子湯」と一緒に服用するか、または「抑肝散」や「逍遥散」に変更します。
陽虚タイプ:
「人参湯(冷えが強い人は附子人参湯)」や建中湯類(大建中湯・小建中湯・黄耆建中湯)から
選択します。脾腎陽虚(頻尿などの腎陽虚の症状を伴うタイプ)に発展している人は「真武湯」を用います。
陰虚タイプ:
本来は「一貫煎」に「芍薬甘草湯」を組み合わせたものを用いるですが、日本では「麦門冬
湯」に「芍薬甘草湯」を組み合わせたもので代用します。
咳嗽の漢方薬治療
各証タイプに対応した漢方薬については、日本で製品化されているものを中心に紹介しますので、中国などで煎じ薬として処方されるものとは異なる部分があります。
風寒タイプ:
風寒の病邪を取り除くには、温めながら発汗を促しますが、これを「散寒解表=さんかんげひょう」といいます。この作用をもつ代表的な漢方薬が「麻黄湯」です。もしさらに鎮咳作用を強めたい場合は、これに「桔梗湯」を加えます。痰が多い場合は「小青竜湯」を使います。また虚弱体質の人の場合は「参蘇飲」なども有効です。
風熱タイプ:
風熱の病邪を取り除くには、冷やしながら発汗を促しますが、これを「清熱解表=せいねつげひょう」といいます。清熱解表剤の中でセキに汎用されるのが「桑菊飲」ですが、日本にはこの製品がないので「麻杏甘石湯」や「五虎湯」で代用します。発熱や咽の痛みが強い人は「銀翹解毒散」(一般薬のため処方箋では服用できません)がいいでしょう。また、少し長引いた場合は「辛夷清肺湯」に変更します。
燥邪タイプ:
「杏蘇散」を用いるのですが、熱性が強い場合(症状では痰に血が混じったり熱が高いもの)は「桑杏湯」を用います。日本では「杏蘇散」を製品にしているメーカーが少ないので(一般薬のため処方箋では服用できません) 見つけにくいかもしれません。「桑杏湯」は製品化されていないため「清肺湯」代用します。
痰濁タイプ:
去痰に優れる「二陳湯」をベースに、鎮咳作用のある「桔梗湯」を加えたものを用います。痰火タイプになっている場合は、「温胆湯」と「桔梗石膏湯」を組み合わせて用いるといいでしょう。
気虚タイプ:
「六君子湯」に「桔梗湯」を加えたものを用います。肺の気虚タイプでカゼを引きやすい人は、「玉併風散」(一般薬のため処方箋では服用できません。商品名は衛益顆粒などがある)に「桔梗湯」を加えてもよいでしょう。
陰虚タイプ:
「麦門冬湯」に「桔梗湯」を加えたものを用います。もし、肺腎陰虚に進んでいる場合は、麦味地黄丸(一般薬のため処方箋では服用できません。商品名は八仙丸などがある) に「桔梗湯」を加えたものに変更するといいでしょう。
ただし、製品化されたものは個人対応ができません。効き目が悪い人や病証タイプが複雑化している人は、当店のような専門店に依頼して、煎じ薬で調節してもらうほうがいいでしょう。
鼻淵の漢方薬治療
鼻淵の治療には、体質や病証に見合った漢方方剤に加えて、通鼻止涕(=つうびしてい:鼻竅を通して鼻水を止める)作用のある生薬が必要です。煎じ薬で服用する場合は、その作用をもつ辛夷・蒼茸子・白芷などの生薬を一緒に煎じて服用すれば解決します。しかし、製品化されたものを使う場合には、それを構成している生薬に注目する必要があります。もし、その漢方方剤を構成する生薬の中に通鼻作用のあるのものが含まれていない場合は、通鼻に特化した製品である「鼻淵丸」や「鼻淵膏」(商品名は各社で少々異なる)などを一緒に服用しないと効果が落ちることになります。以上の点を考慮したかたちで、各タイプにみあった漢方薬(製品化されたもの)を紹介することにします。
風寒タイプ:
「小青竜湯」に、通鼻の「鼻淵丸」や「鼻淵膏」を加えて用います。また虚弱体質の人がカゼを引いて起きた鼻淵は「小青竜湯」を「香蘇散」に変更するとよいでしょう。
風熱タイプ:
「銀翹散」(製品名は銀翹解毒散、銀翹解毒錠)に、通鼻の「鼻淵丸」や「鼻淵膏」を加えて用います。
湿熱タイプ:
「平胃散」と「黄連解毒湯」を合わせたものに、さらに通鼻の「鼻淵丸」や「鼻淵膏」を加えて用います。熱化が強く、どろっとした濃い鼻水が出る人は、「荊芥連翹湯」を用いてもよく、場合によってさらに「鼻淵丸」や「鼻淵膏」を加えます。
気虚タイプ:
「補中益気湯」に、通鼻の「鼻淵丸」や「鼻淵膏」を加えて用います。肺気虚タイプでカゼを引きやすい人は、補中益気湯を「玉併風散」(一般薬のため処方箋では服用できません。商品名は衛益顆粒などがある)に変更し、脾気虚で鼻水の量が多く、下痢やむくみを伴う人は、補中益気湯を「参苓白朮散」や「香砂六君子湯」に変更するといいでしょう。
ただし、製品化されたものは個人対応ができません。効き目が悪い人や病証タイプが複雑化している人は、当店のような専門店に依頼して、煎じ薬で調節してもらうほうがいいでしょう。
認知症の漢方薬治療
認知症に用いる漢方薬について、まず各タイプに見合った製品化されたものを簡単に紹介します。
肝腎不足タイプ:
本来は「七福飲」「河車大造丸」などを用いるのですが、日本で製品化されたものはないため、「六味地黄丸」または「杞菊地黄丸」に、「参茸補血丸」や「亀鹿二仙膠」などを加えて使用します。虚熱が強い人は、六味地黄丸を「知柏地黄丸」に変更します。ただし、六味地黄丸以外は保健薬ではないため、病院の処方箋では服用できません。
脾腎両虚タイプ:
本来は「還少丹」を用いるのですが、日本で製品化されたものはないため、「六味地黄丸」または「杞菊地黄丸」に、「帰脾湯」を加えて使用します。陽虚が強い人は、六味地黄丸を「八味地黄丸」に変更します。
痰濁タイプ:
本来は「滌痰湯」を用いるのですが、日本で製品化されたものはないため、「温胆湯」か、あるいは脾胃が虚弱な人は「半夏白朮天麻湯」を用います。
血瘀タイプ:
本来は「通竅活血湯」を用いるのですが、日本で製品化されたものはないため、「冠心Ⅱ号方」か「血府逐瘀湯」(どちらも保健薬ではなく、商品名は各社によって異なる)を用います。
以上は簡単な漢方薬の紹介ですが、難しい疾患ですので、通常のものだけでは作用が及ばないため、次の二つの点を考慮する必要があります。一つ目は、一般の髄海不足による疾患に比べて、さらにこれを滋補するための配合を強化することです。二つ目は、動物生薬を配合することです。動物生薬は「血肉有情の品」といわれ、植物にはない意思があるため、精神系統の疾患に対してより有効性が高いと考えられています。認知症に用いる動物生薬には鹿角膠・阿膠・亀板膠・紫河車・麝香・牛黄・地竜・全蝎・蜈蚣・白僵蚕・水蛭などがあります。これらは、作用的には一つのジャンルではなく、それぞれ滋補・開竅・熄風・活血などの分類に属していますので、体質に見合ったものを選択して用います。
尚、このような細かい配合は、エキス剤のみでは対応しかねることが多いので、できれば煎じ薬を扱っているような専門の病院や漢方薬局に相談することをお勧めします。
不眠症の漢方薬治療
貴方の病気のタイプのところでも紹介したように、不眠は神明の失調ですので、これを治療する漢方薬には、病証タイプを調整する生薬と神明を安寧させる作用がある生薬とが必要になります。神明を安寧させる作用がある生薬のうち、実証に用いることが多いものには、磁石(じせき)、龍骨(りゅうこつ)などの「重鎮安神薬」と牡蛎(ぼれい)などの「平肝薬」、および黄連(おうれん)などの清心作用をもつ「清熱薬」があります。虚証に用いるものには、酸棗仁(さんそうにん)、柏子仁(はくしにん)、遠志(おんじ)、合歓皮(ごうかんひ)などの「養心安神薬」と夜交藤(やこうとう)などの安神作用をもつ「補血薬」があります。
これによってお分かりでしょうが、たとえ病証タイプに見合った漢方処方であっても、その処方の中に神明を安寧させる生薬が少ない場合は、それをさらに追加しないと効果が半減します。ここでは各タイプ毎に製品化されたものを中心に簡単に紹介しますが、自分の病状が複雑な場合や、含まれる生薬の分量が心配な方は、専門家に相談することをお勧めします。
心脾両虚タイプ:
「帰脾湯」か「加味帰脾湯」を用います。
心胆気虚タイプ:
「安神定志丸」という日本では作っていない処方を用いるのですが、残念ながら日本の既製品の中に代用できそうなものはありませんので、専門家に相談されるようお勧めします。
痰火タイプ:
「竹茹温胆湯」か「温胆湯」を用いますが、温胆湯の場合は黄連末や山梔子末を合わせて服用する必要があります。
肝火タイプ:
「竜胆瀉肝湯」と「柴胡加竜骨牡蠣湯」を合わせて用います。
心腎不交タイプ:
「天王補心丹」を用いますが、腎陰の衰えよりも心火の亢盛のほうが強い場合は、さらに「六神丸」を合わせて服用します。
脳循環障害(脳梗塞・脳出血)後遺症の漢方薬治療
貴方の病気のタイプのところでも紹介したように、意識障害がある中臓腑では、漢方薬の服用は困難ですので、脳循環障害に対する漢方薬の治療は、後遺症である中経絡のものに限定して紹介します。
肝陽上亢タイプ:
日本の既製品の中から選ぶとすると、「柴胡加竜骨牡蠣湯」と「竜胆瀉肝湯」を合わせて服用するか、「降圧丸」(市販薬で、保険薬にはありません)なども応用できます。中国では、「鎮肝熄風湯」や「天麻鈎藤飲」が代表的な処方として使われます。
気虚タイプ:
中国では、「補陽還五湯」が代表的な処方として使われますが、日本の既製品の中に単独でこれに代用できるものはありません。そこで補陽還五湯の生薬構成を参考にすると、黄耆を大量に使い、これに活血(瘀血を除く)作用のある生薬を少量配合していますので、黄耆の粉末と、「折衝飲」や「冠元活血丸または冠元顆粒」などの活血剤とを購入し、5対1の分量比になるようにして服用するといいでしょう。黄耆は、補気薬の中でも利水作用に加えて特に推動作用に優れるという特性をもった生薬です。
湿熱タイプ:
「竹茹温胆湯」か「温胆湯」を用い、これに開竅作用がある牛黄製剤(六神丸など)を合わせて服用するといいでしょう。
腎水虚損タイプ:
「杞菊地黄丸」(市販薬で、商品名は各社によって異なります)で応用できますが、ほてりやのぼせなどの虚熱症状が強い場合は「知柏地黄丸」の方がいいでしょう。
尚、麻痺が強く残っている場合は、漢方薬だけで対応するのには限界がありますので、直接通絡ができる鍼灸治療と併用することをお勧めします。
頭痛の漢方薬治療
頭痛に用いる漢方薬について、まず各タイプに見合った製品化されたものを簡単に紹介します。
(1) 外感性の頭痛
風寒タイプ:
通常の感冒に用いる「葛根湯」でも有効ですが、頭痛専用の「川芎茶調散」のほうが効果がよいでしょう。風湿タイプになっている場合は、本来「羗活勝湿湯」がよいのですが、日本には製品化されたものがありませんので、川芎茶調散に「苓桂朮甘湯」を合わせて服用してみてください。
風熱タイプ:
非保険薬ですが、「銀翹解毒散」(錠剤のものは銀翹解毒錠)が市販されていますので、これを使ってみてください。
(2) 内傷性の頭痛
肝陽タイプ:
本来は「天麻鈎藤飲」を使うのですが、日本には製品化されたものがありませんので、「釣藤散」か「柴胡加竜骨牡蠣湯」で代用します。
痰湿タイプ:
代表的な方剤である「半夏白朮天麻湯」が製品化されていますので、これを使ってください。
瘀血タイプ:
本来は「通竅活血湯」を使うのですが、日本には製品化されたものがありませんので、活血剤に分類される「折衝飲」や「冠元活血丸または冠元顆粒」などが市販されていますので、これで代用します。
気血両虚タイプ:
「十全大補湯」を用いるといいでしょう。ただし胃腸が弱く内臓下垂があり、気血を頭部に上げる力が弱い人は「補中益気湯」を使ってください。
腎虚タイプ:
「杞菊地黄丸」(市販薬で、商品名は各社によって異なります)を使って、じっくり治してください。
以上が基本的な漢方薬になりますが、さらに疼痛部位を考慮して治療したい場合は、煎薬を扱う専門店で、部位ごとの生薬を配合してもらうとよいでしょう。一般に、少陽頭痛には柴胡・黄芩・川芎などの生薬、太陽頭痛には羗活・蔓荊子・川芎などの生薬、陽明頭痛には葛根・白芷・知母などの生薬、厥陰頭痛には呉茱萸・藁本などの生薬がそれぞれ有効とされています。
眩暈(めまい)の漢方薬治療
眩暈の漢方薬について製品化されたものを簡単に紹介しますが、これを見ると頭痛に用いるものとほぼ同じだと気が付くでしょう。以前にも紹介しましたが、中医学では「異病同治」といって、病気が違っていても、原因や病証タイプが共通していれば同じ治療が有効になることがあるとしています。
ただし、主訴に対していうと、頭痛には「通絡」がないと痛みが止まらないのと同様に、眩暈には「熄風」がないと有効性が下がりますので、成分の中にそうしたジャンルの生薬が少ない場合には、それを追加する必要があります。
肝陽タイプ:
本来は「天麻鈎藤飲」を使うのですが、日本には製品化されたものがありませんので、「釣藤散」か「柴胡加竜骨牡蠣湯」で代用します。
痰湿タイプ:
代表的な方剤である「半夏白朮天麻湯」が製品化されていますので、これを使ってください。
気血両虚タイプ:
「十全大補湯」を用いるといいでしょう。ただし胃腸が弱く内臓下垂があり、気血を頭部に上げる力が弱い人は「補中益気湯」を使ってください。
腎虚タイプ:
「杞菊地黄丸」(市販薬で、商品名は各社によって異なります)を使って、じっくり治してください。
以上が基本的な漢方薬になりますが、治療効果がよくない人は、煎薬にして、熄風(内風を除く)のための「平肝熄風薬」というジャンルの生薬を増量するかさらに数種を追加してください。平肝熄風薬のうち眩暈に使うものには、羚羊角(れいようかく)、石決明、牡蠣(ぼれい)、釣藤鈎(ちょうとうこう)、天麻、蒺藜子(しつりし)、白菊花などがあります。
秋の感冒の漢方薬治療
普段からカゼを引くと咳が出やすい人は、秋の感冒で乾燥が肺に影響してしまうため、通常用いる「葛根湯」など発汗性の強い漢方薬を使うときには注意が必要です。
本来の処方としては、涼燥タイプには「杏蘇散」、温燥タイプには「桑杏湯」が用いられるべきですが、日本には製品化されたものがありません。そこで、涼燥タイプには「香蘇散」、温燥タイプには「銀繞解毒散」を選択し、これといっしょに少量の「麦門冬湯」を服用するといいでしょう。
※民間療法の「ねぎ湯」や「しょうが湯」をよくカゼに使う人は、この時期だけ蜂蜜を溶かして服用することで乾燥を緩和することをお勧めします。
冷え症の漢方薬治療
冷え症に用いる漢方薬について、各タイプに見合った製品化されたものを簡単に紹介しますが、経験上、元々冷え症の人が冬の寒さに一度見舞われてしまうと、春になるまでなかなか改善しにくいのも事実ですので、本格的に寒くなる前に服用し始めることをお勧めします。
寒湿タイプ:
日本で製品化されている方剤の中では「苓姜朮甘湯」が下半身の寒湿に有効です。浮腫が強く尿が出にくい人は「五苓散」も有効です。
陽虚タイプ:
脾胃(胃腸)を中心に手足が冷える人は、「桂枝人参湯」や「呉茱萸湯」などの温裏剤に属する方剤を用います。腰の冷えや頻尿などを伴う人は、腎陽の衰退を伴うことが予想されますので「真武湯」のほうがいいでしょう。
肝鬱タイプ:
このタイプに汎用されるのが「四逆散」です。四逆というのは四肢厥逆(=ししけつぎゃく)の略で、手足が冷えることを現しています。「四逆」の名前が付いた方剤には、ほかに「四逆湯」や血虚タイプに用いる「当帰四逆湯」がありますが、それぞれ用途が違いますので、混同しないよう注意が必要です。
瘀血タイプ:
本来なら「生化湯」がよいのですが、日本では製品化されていませんので、「桂枝茯苓丸」とできればこれに「炮附子末」(錠剤ではアコニサン錠)をいっしょにして服用するといいでしょう。もし、下半身は冷えるが、全身的に温めると、上半身はかえってのぼせてしまうような「冷えのぼせ」ぎみの人は、「温経湯」にしてください。
血虚タイプ:
代表的な方剤は「当帰四逆湯」ですが、日本では「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」が市販されていますので、これを用いるといいでしょう。このタイプの人が、間違って寒湿タイプに用いる苓姜朮甘湯や陽虚タイプに用いる人参湯などを長期に服用すると、かえって血虚が進んで陰虚証になることもありますので、体質を自己判断しにくい場合には、一度専門家に見てもらうことをお勧めします。
便秘の漢方薬治療
実熱タイプ:
日本で製品化されている方剤の中では「大黄甘草湯(市販薬ではタケダ漢方便秘薬)」「調胃承気湯」が使われます。作用が緩和なものを希望する人には、「麻子仁丸」がよいでしょう。また、肥満傾向の人には「防風通聖散」がダイエットも兼ねて使われます。
肝鬱タイプ:
このタイプ専門に使う「六磨湯」などの方剤は日本では製品化されていません。そのため単独の方剤では対応できませんので、「四逆散」と「麻子仁丸」を一緒に服用するといいでしょう。徐々に腸の緊張が取れてくれば「麻子仁丸」の分量を減らしていくことができます。
食滞タイプ:
このタイプ専門に使う「枳実導滞丸」などの方剤も日本では製品化されていません。そこで消食作用のある「加味平胃散」(平胃散ではダメ)と「麻子仁丸」を一緒に服用するといいでしょう。
血虚タイプ:
日本で製品化されている方剤の中では「潤腸丸(潤腸湯)」がよいでしょう。老人性の場合は「六味地黄丸」や「杞菊地黄丸」などを合わせて服用するとさらに効果が高まります。また、心血が消耗して精神疲労がある人は「柏子養心丸」や「帰脾湯」などをいっしょに服用するとよいでしょう。
気虚タイプ:
本来なら「黄耆湯」がよいのですが、日本では製品化されていませんので、「補中益気湯」を蜂蜜といっしょに服用することをお勧めします。
陽虚タイプ:
本来なら「大黄附子湯」がよいのですが、日本では製品化されていませんので、「大黄甘草湯」に「炮附子末(病院ではアコニサン錠)」を加えて服用するとよいでしょうし、かえってそれぞれの分量比率を症状に応じて調節することができますので、そのほうがいいかもしれません。
【 記事一覧へ 】