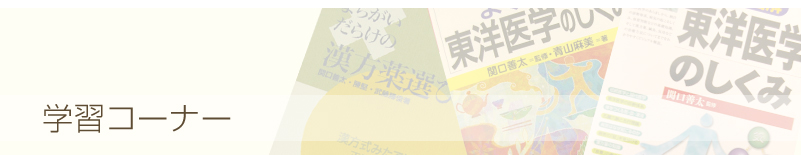学習コーナー
婦人科の鍼灸治療 [鍼灸の知識]
生理痛の鍼灸治療
まず、生理痛の鍼灸治療のタイミングについてご紹介します。日本の鍼灸治療は、通常1週間に1回の割合で行いますが、こと婦人科に関しては、月経の周期を考慮したほうが効果的なことが多いのです。そこで、生理痛についていうと、とくに実証の場合には、月経前に集中させたほうがいいでしょう。例えば、週に1度治療することを考えるならば、1ヶ月分の4回を月経前の10日間ほどの期間にまとめて受療してみてください。これだけまとめて治療しても、その後の生理で痛みが何も変わらないようであれば、診断が間違っているか技術が足りないと判断できるので、鍼灸師のレベルを見極めるにも有効です。
生理痛の鍼灸治療では、子宮に気血を流入する「衝任脈」の流れを改善することが止痛に直結しますので、衝任脈上の下腹部にある経穴(気海・関元・中極・気穴など)が鎮痛のためのツボということになります。したがって、それぞれの証タイプに対応する処方は、これらと下記にある証タイプに対応する経穴とを組み合わせたものになります。
寒湿タイプ:
上記の経穴に加えて、痰湿を除く経穴(豊隆・陰陵泉など)に瀉法を施したうえ、さらに温法(灸頭針やお灸で温める)を施します。
肝鬱タイプ:
上記の経穴に加えて、気滞を除く経穴(太衝・間使など)に瀉法を施します。
瘀血タイプ:
上記の経穴に加えて、瘀血を除く経穴(血海・三陰交など)に瀉法を施します。痛みが特
にひどい場合は、さらに帰来などの疼痛局部に近い経穴を加えます。
(気滞血瘀の場合は肝鬱タイプも参照してください)
陽虚タイプ:
陽気を補う経穴(命門・腎兪など)に補法と温法を施すほか、上記の下腹部の経穴にも温補を積極的に行います。
肝腎不足タイプ
上記の経穴に加えて、腎精や肝血を補う経穴(太谿・三陰交など)に補法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
月経不順(経早)の鍼灸治療
経早の鍼灸治療では、子宮に気血を流入する「衝任脈」の流れを改善することと月経の本体である血を整えることを図って、衝任脈上の下腹部にある経穴(関元または中極など)と、血病に常用する経穴(血海など)を配穴します。実証の場合にはこれらに瀉法を施し、虚証では補法を施します。
それぞれの病証タイプに対応する処方は、上記の経穴と下記の病証タイプに対応する経穴とを組み合わせたものになります。
鬱熱タイプ:
上記の経穴に加えて、鬱熱を除く経穴(行間・太衝など)に瀉法を施します。
実熱タイプ:
上記の経穴に加えて、胃腸の熱を除く経穴(内庭・天枢など)に瀉法を施します。
陰虚タイプ
上記の経穴に加えて、腎陰や肝血を補う経穴(復溜・三陰交など)に補法を施します。
気虚タイプ:
上記の経穴に加えて、脾気を補う経穴(足三里・脾兪など)に補法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
月経不順(経遅)の鍼灸治療
鍼灸で経遅を治療するには、「貴方の病気のタイプ」で紹介している各証タイプに対応するツボと、子宮に直接作用する衝脈や任脈(合わせて衝任脈という)という経絡上のツボを組み合わせて治療します。このうち衝任脈のツボは、証タイプが違っていても共通して用いることが出来ますので、これを先に紹介すると、下腹部の中央にある「気海」または「関元」を利用します。このツボによって子宮に流入する気血(特に血)を整えます。このとき実証に属すタイプの場合は瀉法という若干強めの操作を施し、虚証に属すタイプの場合は補法という穏やかな操作を施します。
個々の証タイプに対応するツボは、下記を参照してください。
肝鬱タイプ:
気滞を除く「太衝」「間使」といったツボを、上記のツボに配合して(配穴という)、どの
ツボにも瀉法を施します。
寒邪タイプ:
血行を促す「血海」「三陰交」といったツボを、上記のツボに配穴して瀉法を施しますが、
さらに寒邪を除くための温法と呼ばれる操作(灸頭鍼など)を加えます。
陽虚タイプ
陽気を補う「命門」「腎兪」などのツボを、上記のツボに配穴して補法を施しますが、積極的に温法を施すと効果が倍増します。
血虚タイプ:
上記のツボに、肝血を補うツボ(三陰交・肝兪など)を配穴して補法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
月経不順(経乱)の鍼灸治療
鍼灸で経乱を治療するには、経早や経遅と同様、「貴方の病気のタイプ」で紹介している各証タイプに対応するツボと、子宮に直接作用する衝任脈の経絡上のツボを組み合わせて治療します。このうち衝任脈のツボは証タイプの違いに関わらず共通で、下腹部の中央にある「気海」や「関元」などを利用します。このツボによって子宮に流入する気血(特に血)を整えます。このとき実証に属すタイプの場合は瀉法という若干強めの操作を施し、虚証に属すタイプの場合は補法という穏やかな操作を施します。
個々の証タイプに対応するツボは、下記を参照してください。
肝鬱タイプ:
気滞を除く「太衝」「間使」といったツボを、上記のツボに配合して(配穴という)、どの
ツボにも瀉法を施します。
腎虚タイプ
腎の精気を補う「太谿」「腎兪」などのツボを、上記のツボに配穴して補法を施します。足腰に冷えを感じるタイプの場合には、さらに「関元」や「腎兪」に灸頭鍼などの温法を加えます。
脾虚タイプ:
上記のツボに、脾気を補う「足三里」「脾兪」などのツボを配穴して、補法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
不妊症の鍼灸治療
不妊症の病証タイプの説明のところでも紹介していますが、不妊症の治療では、月経不順や月経痛または体質の虚弱などがある人は、一定期間は避妊をして、それを調整するような治療を行うことが結果的に妊娠を早めます。もしタイミング療法などと並行した治療を希望される場合は個別対応になり、一般的なものとして紹介することが難しくなりますので、ここで紹介する治療は、その避妊期間を前提としたものになることをご了承ください。
実証タイプの場合、経前期から行経期の前半までの間を中心に治療します。経後期に陰血の補充が必要な人は、虚証の血虚タイプや陰虚タイプで用いるツボをいくつか配合します。虚証タイプでは、陰虚や血虚の場合は経後期を中心に治療し、陽虚の場合は経後期の後半から経前期までの間を中心に治療します。
使うツボは、各証タイプに対応するツボと、下腹部にある「気海」「関元」「中極」「水道」「帰来」などのツボを組み合わせ、実証に属すタイプでは瀉法を施し、虚証に属すタイプでは補法を施します。
個々の証タイプに対応するツボは、下記を参照してください。
肝鬱タイプ:
上記のツボに加えて、気滞を除く「太衝」「間使」などのツボに瀉法を施します。また、気の鬱積が熱化して生理が早まるタイプの人では、鬱熱を除いて血の消耗を防ぐために、「太衝」を「行間」に代えます。
寒邪タイプ:
上記の下腹部のツボに瀉法を施し、寒邪を除くために灸頭鍼のような温法を加えます。
湿邪がからむタイプでは、痰湿を除く「豊隆」「陰陵泉」などのツボをさらに加え、瀉法を施します。
陽虚タイプ:
上記のツボに加えて、腎の精気を補う「太谿」「腎兪」などのツボに補法を施します。さらに「関元」や「腎兪」などに温法を加えます。
陰虚タイプ:
上記のツボに加えて、腎陰や肝血を補う「復溜」「三陰交」などのツボに補法を施します。また、不正出血がみられるような場合は、「隠白」などに瀉法を施します。
血虚タイプ:
上記のツボに加えて、肝血を補う「三陰交」「肝兪」などのツボに補法を施します。また、血を生産する脾気の虚弱が見られる場合は、さらに脾気を補う「足三里」「脾兪」などのツボにも補法を施します。
※不妊の鍼灸治療では、よくお灸を用いているところがありますが、このお灸という方法、寒邪タイプや陽虚タイプといった寒証には非常によい方法ですが、熱証である陰虚タイプでは逆効果の場合もありますので、鑑別には注意が必要です。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
不育症の鍼灸治療
不育症の考え方でも説明したように、不育症の治療では、しばらくの間は妊娠を避けて、先天の源と後天の源を中心にして身体の回復をはかる必要があります。
そのために先天の源を補う「腎兪」と後天の源を補う「脾兪」、さらに全身の気血を補う「足三里」の補法が重要になります。この3つのツボをベースに、以下に紹介するそれぞれのタイプの相違に対応するツボを配穴して治療します。
①陰虚タイプ:
基本的な3つのツボに、腎陰を補うための「復溜」「血海」などのツボを配穴し、補法を施します。ほかのタイプにはお灸をしてもよいのですが、このタイプにはお灸を用いないのが注意点です。
②脾腎両虚タイプ:
基本的な3つのツボに、腎の精気を補うため腹部にある「関元」「気海」などのツボを配穴し、補法を施します。このタイプには、腹部や腰背部のツボにお灸を施すことも有効です。とくに下腹部や腰の冷えや下痢しやすいなどの陽虚の症状を伴う人は、普段から自分でせんねん灸などを行うのもいいでしょう。(ツボは鍼灸師に教えてもらったほうが正確です)
③気血不足タイプ:
基本的な3つのツボに、気を補う「合谷」「気海」、血を補う「三陰交」「肝兪」などのツボを病態に合わせて配穴し、補法を施します。このタイプにも、腹部や腰背部のツボにお灸を施すことも有効です。
不育症の人が妊娠した場合の鍼灸治療
まず腹部のツボへの刺針は避けて、もし使う場合でも灸法に替えます。鍼灸では漢方薬と異なって、特別に「安胎」の作用があるツボはありませんが、先天の源である腎のもつ「封蔵」という作用と、後天の源である脾のもつ「統血」という作用を強めることが、安胎につながりますので、不育症のそれぞれのタイプに対する治療穴に加えて、「腎兪」や「脾兪」「足三里」などのツボを重要視して用います。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
更年期障害の鍼灸治療
更年期障害を治療するには、腎陰虚証か腎陽虚証の判別に合わせた対応と、衝任脈の調節が必要ですので、これに基づく基本的な鍼灸の処方(ツボの組み合わせ)を紹介します。
腎陰虚タイプでは「太谿」「復溜」「三陰交」「気海」「関元」などからいくつか選択して処方を組み、腎陽虚タイプでは「太谿」「腎兪」「命門」「気海」「関元」などからいくつか選択して処方を組み、補法を施します。もし、陰陽両虚に進行している場合は、この2つのタイプの処方を織り交ぜて治療することができます。
腎陰虚タイプ⇒「太谿・腎兪・気海・関元」+復溜・三陰交
腎陽虚タイプ⇒「太谿・腎兪・気海・関元」+命門
ツボの働きとしては、「太谿」「腎兪」は腎の虚に対して腎陰虚・腎陽虚ともに対応でき、「復溜」「三陰交」は腎精や腎陰を補充し、「命門」は腎陽を温めながら補い、「気海」「関元」は衝任脈を調節します。
次に、陰陽失調の進行に対応する主なツボを紹介します。
①肝の熱の亢進を伴う人(めまい・耳鳴りがこれによる症状):
めまいでは「風池」「行間」など、耳鳴りでは「聴会」「行間」などの瀉法を腎陰虚タイプの処方に加えます。
②心の熱の亢進を伴う人(動悸・不眠がこれによる症状):
「神門」などの瀉法を腎陰虚タイプの処方に加えます。
③脾の冷えを伴う人(食欲不振・むくみ・軟便や下痢がこれによる症状):
「足三里」「脾兪」などの補法を腎陽虚タイプの処方に加えます。
④皮膚の乾燥や痒みや蟻走感(皮膚を蟻が這い回るような感覚)を覚える人:
「曲池」「血海」などの瀉法を腎陰虚タイプの処方に加えます。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
月経前症候群(経前情緒失調)の鍼灸治療
月経前症候群を鍼で治療するには、適応する処方の選択と操作が必要です。その処方は、生理がスムーズに始まるためのツボ(衝任脈という経絡の上にあるツボ)をベースに、これに皆さん個々の体質(「貴方の病気のタイプ」で紹介している病証タイプ)に対応するツボを組み合わせたもので構成されます(組み合わせることを「配穴」といいます)。このうち衝任脈上のツボは、どのタイプにも共通して「気海」や「関元」などを用いることができます。
体質タイプに応じて用いるツボは下記のとおりで、操作はタイプの虚実に合わせて、瀉法と補法を使い分けます。
①気滞タイプ:
気滞を除くツボには「太衝」「間使」などがあり、これを共通するツボと配穴します。操作は、瀉法を施します。
このタイプの中には、乳房の張りや痛みが強い人や、気滞が熱化してめまいや頭痛などを伴う人もいますので、その場合はツボを追加したり変更したりして対応します。
②痰火タイプ:
痰湿を除く「豊隆」「陰陵泉」などのツボと、熱を除く「合谷」「曲池」などのツボを共通するツボと配穴し、これらに瀉法を施します。
このタイプの中には、悪心やむくみなどを伴う人もいますので、その場合はツボを追加したり変更したりして対応します。
③血虚タイプ:
血を補って心神の安寧(精神の調節)をはかる「三陰交」「心兪」や、血の生産を促す「足三里」などのツボを選び、共通するツボと配穴して、これらに補法を施します。
以上が一般的な処方ですが、人によって精神症状が激しい場合は、さらに「四神聡」などを配穴して、心神の安寧をはかります。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
子宮筋腫・卵巣膿腫(癥瘕) の鍼灸治療
局所または下腹部のツボと、発症の原因に対応するツボを組み合わせて治療します。
局所とは、筋腫が比較的大きくて手で触れて塊りが分るような場合で、その塊りの周囲が鍼を刺すポイントとなります。触っても分らないような場合は、衝任脈(子宮に気血を運ぶルート)上の下腹部にあるツボ(気海・関元・中極など)から選びます。この部位の操作は、どのタイプでも基本的には瀉法を行います。
発症の原因に対応するツボとは、下記にある、「貴方の病気のタイプ」で紹介している病証タイプに対応するツボのことです。
①瘀血タイプ:
瘀血を除くためには「三陰交」「血海」などへの瀉法の操作が必要で、これを局所または下腹部のツボと組み合わせます。
②気滞タイプ:
気滞を除くためには「太衝」「間使」などへの瀉法の操作が必要で、これを局所または下腹部のツボと組み合わせます。
③痰湿タイプ:
痰湿を除くためには「豊隆」「陰陵泉」などへの瀉法の操作が必要で、これを局所または下腹部のツボと組み合わせます。
以上が基本的なタイプ別の治療ですが、病状が複雑化している人では、①~③が混在していることもありますので、その場合は相互にツボを組み合わせて用います。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
帯下病の鍼灸治療
実証に属すタイプの帯下病を鍼で治療するには、任脈を通して子宮の湿邪に直接作用する「中極」と、下記①②のタイプに対応するツボを組み合わせます。虚証に属すタイプの帯下病を鍼で治療するには、帯脈によって帯下が漏れ出るのを抑える「帯脈」というツボを、下記③④⑤のタイプに対応するツボに組み合わせます。
①痰湿タイプ:
上記のツボに、痰湿を除く「豊隆」「陰陵泉」などのツボを組み合わせて瀉法を施します。
②湿熱タイプ:
上記のツボに、痰湿タイプのツボ(①参照)と、熱を除く「合谷」「曲池」などを組み合わせて瀉法を施します。ストレスによる鬱熱が影響してこのタイプになっている人は、痰湿タイプのツボと、鬱熱を除く「行間」などを組み合わせて瀉法を施します。
③気虚タイプ:
上記のツボに、脾気を補う「足三里」「脾兪」などのツボを組み合わせて補法を施します。
④陽虚タイプ:
腎の陽虚タイプでは、上記のツボに「関元」「腎兪」などを組み合わせて補法と温法(灸頭鍼など)を施します。脾の陽虚タイプでは、組み合わせを「神闕」「足三里」などにして、同様に補法と温法を施します。脾腎陽虚タイプなら両方のタイプのツボを組み合わせます。
⑤陰虚タイプ:
上記のツボに、腎陰を補う「復溜」「三陰交」などのツボを組み合わせて補法を施します。ただし温法は乾燥を促すことがあるため、このタイプには用いません。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
【 記事一覧へ 】