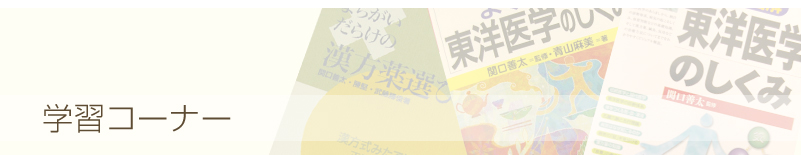学習コーナー
内科系の鍼灸治療 [鍼灸の知識]
胃痛・腹痛の鍼灸治療
胃痛・腹痛に用いる経穴の処方(ツボの組み合わせ)は、経絡中の気血運行を促して鎮痛をはかるためのものと、証タイプの相違に対応して原因に対処するものとで構成されます。経絡中の気血運行を促す経穴は、患部付近のものが中心で、「上脘」「中脘」「下脘」「天枢」「帰来」などの中から通常は最も近いもの選ぶか、または経穴でなくても痛む部位そのものに刺すことも多く、この場合は「阿是穴」と呼んでいます。操作は、実証には瀉法、虚証には補法を施します。
これに組み合わせるように、下記の証タイプの相違に対応するものを選択します。
寒邪タイプ:
胃寒を除く作用のある経穴(例えば関元・胃兪)を用いて、温法(灸頭針やお灸で温める)による瀉法を施します。これは鎮痛のための経穴にも行います。
肝鬱タイプ:
気滞を除く作用のある経穴(例えば内関・太衝)を用い、これに瀉法を施します。
陽虚タイプ:
脾陽を補う作用のある経穴(例えば神闕・脾兪)を用いて、温法による補法を施します。これは鎮痛のための経穴にも行います。
陰虚タイプ:
陰液を補う作用のある経穴(例えば足三里+復溜)を用い、これに補法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
病証タイプ | 鎮痛をはかるための経穴 | 証タイプに対応した代表的な経穴 |
寒邪タイプ | 患部付近の経穴 (上脘・中脘・下脘・天枢・帰来) 疼痛局部(阿是穴) <実証には瀉法、虚証には補法> | 関元・胃兪<温法+瀉法> |
肝鬱タイプ | 内関・太衝<瀉法> | |
陽虚タイプ | 神闕・脾兪<温法+補法> | |
陰虚タイプ | 足三里+復溜<補法> |
咳嗽の鍼灸治療
咳嗽に用いる経穴の処方(ツボの組み合わせ)は、上逆した肺気を下降(降逆という)させて鎮咳をはかるためのものと、証タイプの相違に応じてそれぞれの原因に対処するものとで構成されます。
肺気の降逆を促すための経穴は、胸背部や肺経のものが中心で、「中府」「肺兪」「天突」「尺沢」などがそれにあたります。各証に応じる経穴は下記のようにします。臨床では、患者それぞれの細かい病状に合わせて、両方のものの中からいくつかを選択して処方とします。操作は、実証には瀉法、虚証には補法を施します。
風寒タイプ:
風寒を除く散寒解表作用のある経穴(例えば大椎・大杼・合谷)を用いて、温法(灸頭針やお灸で温める)による瀉法を施します。
風熱タイプ:
風熱を除く清熱解表作用のある経穴(例えば風池・大椎・合谷)を用い、これに瀉法を施します。熱を除かなければならないので、温める作用のあるお灸はあまり使いません。
痰濁タイプ:
去痰作用に優れる経穴(例えば豊隆・中脘)を用いて、瀉法を施します。痰火になっている場合は、これに内庭などの胃熱を除く経穴を配穴(ツボを組み合わせること)します。
気虚タイプ:
肺の虚に用いる経穴(例えば太淵・肺兪)に、気を補う作用のある経穴(例えば合谷・足三里)を配穴し、これに補法を施します。
陰虚タイプ:
肺の虚に用いる経穴(例えば太淵・肺兪)に、陰液を補う作用のある経穴(例えば復溜、太谿)を配穴し、これに補法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
病証タイプ | 鎮咳をはかるための経穴 | 証タイプに対応した代表的な経穴 |
風寒タイプ | 胸背部や肺経の経穴 (中府・肺兪・天突・尺沢など) <実証には瀉法、虚証には補法> | 大椎・大杼・合谷<温法+瀉法> |
風熱タイプ | 風池・大椎・合谷<瀉法> | |
痰濁タイプ | 豊隆・中脘<瀉法> 痰火の場合→+内庭<瀉法> | |
気虚タイプ | 太淵・肺兪+合谷・足三里<補法> | |
陰虚タイプ | 太淵・肺兪+復溜・太谿<補法> |
鼻淵の鍼灸治療
鼻淵に用いる経穴の処方(ツボの組み合わせ)は、鼻竅を通して鼻水を止める「通鼻止涕(=つうびしてい)」をはかるためのものと、証タイプの相違に応じてそれぞれの原因に対処するものとで構成されます。
通鼻止涕のための経穴は、鼻の付近のもの(例えば迎香・上迎香)が中心で、場合によって前額部のもの(例えば上星・印堂)を加えて、これらに瀉法を施します。
証タイプの相違に対応する経穴は、異病同治の考え方に基づいて、同じ肺系統の疾患である咳嗽とほとんど変わりませんので、ここでは咳嗽の項目で紹介が少なかった湿熱タイプについてのみ紹介します。
湿熱タイプ:
痰湿を除く作用のある経穴と熱邪を除く作用のある経穴との配穴(例えば陰陵泉+内庭、豊隆+曲池)に、瀉法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
病証タイプ | 通鼻止涕をはかるための経穴 | 証タイプに対応した代表的な経穴 |
湿熱タイプ | 鼻の付近や前額部の経穴 (迎香・上迎香・上星・印堂など) <瀉法を施す> | 陰陵泉+内庭・豊隆+曲池<瀉法> |
風寒タイプ | 咳嗽の項目参照 | |
風熱タイプ | ||
気虚タイプ |
認知症の鍼灸治療
認知症に用いる処方(ツボの組み合わせ)は、頭部の経穴と、証タイプの相違に応じてそれぞれの原因に対処する体幹部や四肢の経穴とで構成されます。このうち頭部の経穴(風池・百会・完骨・印堂など)には、虚証の場合は補法により益脳をはかり、実証の場合は瀉法により開竅や活血通絡をはかります。各証タイプに対応する主な体幹部・四肢の経穴は次のとおりです。
肝腎不足タイプ:肝兪・腎兪・三陰交・絶骨などから選択して補法を施します。
脾腎両虚タイプ:脾兪・腎兪・足三里・太谿などから選択して補法を施します。
痰濁タイプ:豊隆・陰陵泉・内関などから選択して瀉法を施します。
血瘀タイプ:三陰交・郄門・心兪・膈兪などから選択して瀉法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
不眠症の鍼灸治療
不眠症に用いる処方(ツボの組み合わせ)は、心神を調節するためのものを中心に、これに病証タイプの相違に応じて、影響が及んでいる臓腑を調節するものとで構成されます。
心神の調節をはかるための経穴には、四神聡や安眠などの頭部のものや、神門・心兪・大陵・厥陰兪などの心経・心包経のものがあります。病証タイプの虚実に応じて、これらのうちのいくつかの経穴に、実証なら瀉法、虚証なら補法を施します。
これに加えるための各臓腑の経穴は下記のとおりです。
心脾両虚タイプ:
上記の経穴(補法)に加えて、脾気虚を補う経穴が必要です。これには三陰交・足三里・脾兪などがあります。
心胆気虚タイプ:
上記の経穴(補法)に加えて、胆気虚を補う経穴が必要です。これには丘墟・胆兪・気海などがあります。
心腎不交タイプ:
上記の経穴に瀉法を施して、腎陰を補う経穴に補法を施します。そのための経穴には復溜・太谿などがあります。
痰火タイプ:
上記の経穴(瀉法)に加えて、脾胃から痰と熱を除く経穴が必要です。これには豊隆・中脘・内庭などがあります。
肝火タイプ:
上記の経穴(瀉法)に加えて、肝火を除く経穴が必要です。これには行間などがあります。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
脳循環障害(脳梗塞・脳出血)の鍼灸治療
脳循環障害(脳梗塞・脳出血)の鍼灸治療の中で、非常に好成績を残している方法に「醒脳開竅法=せいのうかいきょうほう」があります。これは中医学の考え方の上に、現代医学によるCTなどの検査を考慮した画期的なもので、30年ほど前に中国の天津で開発されました。中国ではすでに10万例を超す治療が行われている有名な方法となり、今では中国全土から、政府高官をはじめとする多数の患者が受療にやって来るようになりました。
当院では、関口院長が、醒脳開竅法の開発者である石学敏老師が20数年前に初めて来日した頃より、老師の講演や書籍の出版に関わってきたことから、この方法を中心に治療を行ってきました。そこでこれを中心に紹介します。
醒脳開竅法の特徴は、中臓腑に対しても中経絡に対しても有効なことです。それは、処方の中心となる主穴に開竅・滋補肝腎(肝腎の陰を滋養する)・通絡が含まれていることによります。具体的には、清心開竅と上肢の通絡には内関、開竅による脳の覚醒には人中、滋補肝腎と下肢の通絡には三陰交という3穴が組み合わされた処方です。これ以外に、麻痺の部位や嚥下困難・顔面神経麻痺などの症状によって、例えば委中・上廉泉・合谷などのツボを組み合わせます。
醒脳開竅法にはもう1つの特徴として、治療効果をあげるための特別な操作法があります。上記のツボに日本で行われている通常の刺し方をしても、あまり効果は出ません。例えば、開竅させるためには目に涙が浮かぶ程度の刺激が必要になりますし、通絡するには筋肉がピクッと反応する程度のひびき感を得ないといけません。そのために必要となる「捻転と提挿の混合補瀉法」や「飛法」といった特別な操作法を習得することが求められるのです。
現在のところ、日本でこれらの操作法を用いて醒脳開竅法を本格的に行う治療院はまだまだ限られています。もし鍼灸院で醒脳開竅法による治療を受けたいと思われる方は、あらかじめ「捻転と提挿の混合補瀉法」や「飛法」などができるかどうかを確認したうえで、受診されるとよいでしょう。
頭痛の鍼灸治療
外感性の頭痛は一過性のことが多く、一般には鍼灸よりも薬で治療する人が多いので、ここでは内傷性の頭痛について紹介します。
頭痛に用いる処方(ツボの組み合わせ)は、疼痛部付近の経穴と、それぞれの証タイプに対応する経穴とで構成されます。疼痛部付近の経穴には、痛む局所そのものと、その部位が関連する経絡上のツボがあります。場合によって局所がツボの部位と一致することもありますが、既存のツボでなくてもその部位を阿是穴(=あぜけつ)というツボとみなします。疼痛部位が関連する経絡上の代表的なツボには、側頭部が痛む少陽頭痛の場合は風池・率谷、後頭部が痛む太陽頭痛の場合は天柱・晴明、前頭部が痛む陽明頭痛の場合は頭維、頭頂部の痛む厥陰頭痛の場合は四神聡などがあります。
各証タイプに対応する主な経穴は下記のとおりです。
肝陽タイプ:
このタイプの治療には、上記の経穴と、亢進して頭に上昇している肝陽を下ろす太衝・足臨泣などの経穴とを必ず組み合わせなければなりません。頭部のツボだけを使うと、治療しているときはよさそうでも、治療後にかえって頭部が充血して痛みが戻ることも多くみられます。そのため、足先にあるツボを使って頭部に気血が昇っていかないように、下げる必要があるのです。操作はどのツボにも瀉法を施します。
痰湿タイプ:
このタイプの治療には、豊隆・陰陵泉などの痰湿を除く経穴を、疼痛部付近の経穴と組み合わせて瀉法を施します。
瘀血タイプ:
このタイプの治療には、膈兪・三陰交などの瘀血を除く経穴を、疼痛部付近の経穴と組み合わせて瀉法を施します。気滞血瘀の場合には、さらに間使などの気滞を除く経穴を加え(瀉法)ます。
気血両虚タイプ:
このタイプの治療には、合谷・足三里などの気の不足を補う経穴と、膈兪・三陰交などの血の不足を補う経穴を、疼痛部付近の経穴と組み合わせて補法を施します。ただし胃腸が弱く内臓下垂があり、気血を頭部に上げる力が弱い人は、さらに百会の灸法を加えて、気の上昇を促します。
腎虚タイプ
このタイプの治療には、太谿や三陰交など腎精や肝血を補うことのできる経穴と、疼痛部付近の経穴とを組み合わせて補法を施します。もし陰虚になっている場合は、太谿を復溜に変更します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
眩暈(めまい)の鍼灸治療
眩暈に用いる処方(ツボの組み合わせ)は、それぞれの証タイプに対応する経穴をベースに、熄風のための経穴を組み合わせて構成します。
この熄風のための経穴は、風門穴という分類に属すものを多用します。よく使われるものに、風池などの「風」の文字の入ったツボや百会があります。手技については、実証の場合は瀉法を施し、虚証の場合は補法を施します。
各証タイプに対応する主な経穴は下記のとおりです。
肝陽タイプ:
頭にある経穴を用いる場合は、下肢にある太衝・陽輔などの経穴を必ず組み合わせて、上昇した肝陽を下ろすようにします。手技はどのツボにも瀉法を施します。
また、肝腎の陰虚を伴っている場合には、復溜や三陰交の補法を加えます。
痰湿タイプ:
痰湿を除く豊隆・陰陵泉などの経穴と、内関などの清空を開竅させる経穴とを組み合わせて瀉法を施します。痰湿が熱化している場合には、合谷や曲池の瀉法を加えます。
気血両虚タイプ:
足三里・三陰交・合谷などの気血を補う経穴と、熄風作用のある経穴の中で気血を頭部に上げる作用にも優れる百会を組み合わせます。手技は補法を施しますが、百会には灸法を加えるとその作用が強まります。
腎虚タイプ
太谿や三陰交など腎精や肝血を補うことのできる経穴と、風池などの熄風のための経穴とを組み合わせて補法を施します。もし陰虚になっている場合は、太谿を復溜に変更します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
秋の感冒の鍼灸治療
秋の感冒に用いる経穴の処方(ツボの組み合わせ)は、解表をはかるためのものに、肺や皮膚を潤して乾燥を防ぐものを加えます。「涼燥」と「温燥」の各タイプに対応する主な経穴は下記のとおりです。
涼燥タイプ:
散寒解表の作用のある経穴(例えば大椎・大杼・合谷)を用いて、温法(灸頭針やお灸で温める)による瀉法を施します。これに潤いを補う作用のある経穴(例えば復溜)を加え、補法を施します。
温燥タイプ:
清熱解表の作用のある経穴(例えば風池・大椎・合谷)を用いて、瀉法を施します。このタイプでは熱を除かなければならないので、温める作用のあるお灸は通常使いません。これに潤いを補う作用のある経穴(例えば復溜)を加え、補法を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
冷え症の鍼灸治療
冷え症に用いる経穴の処方(ツボの組み合わせ)は、手足の末端部付近にあってその部位の気血の流れの改善や温散をはかるための経穴と、それぞれの証タイプに対応する経穴とで構成されます。
手足の末端部付近の経穴には、合谷・太衝・湧泉・八邪・八風などがあり、温法(灸頭針やお灸で温める)を施します。
各証タイプに対応する主な経穴は下記のとおりです。
寒湿タイプ:
上記の経穴に加えて、痰湿を除く経穴(豊隆・陰陵泉など)に瀉法を施したうえ、さらに温法を施します。
陽虚タイプ:
上記の経穴に加えて、陽気を補う経穴(命門・腎兪・関元など)に補法と温法を施します。
肝鬱タイプ:
上記の経穴に加えて、気滞を除く経穴(内関・気海など)に瀉法を施します。
瘀血タイプ:
上記の経穴に加えて、瘀血を除く経穴(三陰交・膈兪など)に瀉法を施します。気滞血瘀
の場合には、さらに気滞を除く経穴(間使など)に瀉法を加えます。
血虚タイプ:
上記の経穴に加えて、血の不足を補う経穴(三陰交・膈兪など)に補法を施します。場合によっては、全身の温通散寒を促すため、合谷に補法を施したり三陰交に温法を施したりします。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
便秘の鍼灸治療
便秘に用いる鍼灸の処方は、胃腸(特に大腸)の気を下降させて排便を促すための経穴と、それぞれの証タイプに対応する経穴とを組み合わせて構成します。
胃腸の気を下降させる経穴には、天枢・上巨虚・大腸兪などがあります。これらに対する操作は、瀉法を施して阻滞を除くようにします。一般の疾患では虚証には補法を施しますが、便秘の場合には腸内の滞りを除く必要があるため、虚証でも瀉法を施すのです。
各証タイプに対応する主な経穴は下記のとおりです。
実熱タイプ:
上記の経穴に加えて、胃腸の熱を除く経穴(内庭・合谷など)に瀉法を施します。
肝鬱タイプ:
上記の経穴に加えて、気滞を除く経穴(内関・気海など)に瀉法を施します。
食滞タイプ:
上記の経穴に加えて、未消化物の停滞を除く経穴(下脘など)に瀉法を施します。
血虚タイプ:
上記の経穴に加えて、血の不足を補う経穴(三陰交・肝兪など)に補法を施します。
気虚タイプ:
上記の経穴に加えて、胃腸の気を補う経穴(胃兪・脾兪など)に補法を施します。
陽虚タイプ:
上記の経穴に加えて、陽気を補う経穴(関元・腎兪など)に補法と温法(灸頭針やお灸で温める)を施します。
※ツボの選択については、各先生によって様々です。ここに挙げたのは代表的なものであることをご承知下さい。
【 記事一覧へ 】