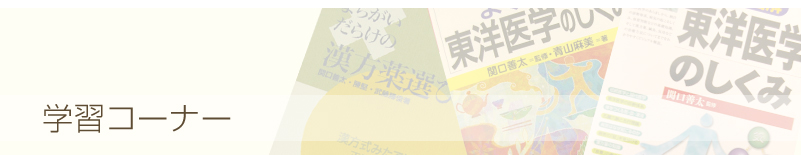学習コーナー
婦人科の漢方薬治療 [漢方薬の知識]
生理痛の漢方薬治療
寒湿タイプ:
「温経湯」や「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」を用いるといいでしょう。普段からこうしたものを服用して冷えを除いていくのですが、これだけだとあまり即効性がありません。そこで、これだけでは痛みがコントロールできないという人は、最初のうちは生理の直前から生理の3日目の期間だけ、「折衝飲」など活血作用(血行を促す作用)の強いものを併用したほうが効果的です。通常、生理が何回か来るうちに段々この薬は使わなくてもよくなります。もし、湿が強く浮腫や軟便などがある人は、普段のベースになる処方を「真武湯」にするといいでしょう。
肝鬱タイプ:
「逍遙散」(または「加味逍遙散」)や「四逆散」「抑肝散」を用いるといいでしょう。これも寒湿タイプで紹介したのと同様で、痛みが強い人には即効性に欠けるため、これだけでは痛みがコントロールできないという人は、最初の数ヶ月間、生理の直前から生理の3日目の期間は「折衝飲」を併用して活血作用を強化すると効果的です。
瘀血タイプ:
本来なら膈下逐瘀湯を用いるタイプですが、日本にはこの製品がないため「血府逐瘀丸」や「折衝飲」で代用します。どちらも病院で処方できる漢方薬ではありませんので、病院から出してもらうとしたら「桂枝茯苓丸」がいいでしょう。ただし、活血作用(血行を促す作用)が折衝飲より劣るので、桂枝茯苓丸では鎮痛できない人は、こちらに変更するほうが効果的です。
陽虚タイプ:
「牛車腎気丸」を用いるといいでしょう。「八味地黄丸」でもいいのですが、牛車腎気丸は八味地黄丸に車前子と牛膝を加えたもので、牛膝には下半身の血行を促す作用があるほか、漢方薬の成分全体を下半身に誘導する作用がありますので、こちらのほうがより効果的です。
肝腎不足タイプ:
日本には肝腎を補って婦人科を調節する専門の漢方薬はありませんので、「杞菊地黄丸」をベースに服用します。しかし、この漢方薬には血行を促して止痛するような生薬があまり配合されていないため、生理期間には「四物湯」を併用するといいでしょう。注意することとして、上記では「折衝飲」を併用していますが、虚証のタイプには作用が強すぎるので、このタイプには肝血を補う作用のある四物湯をお勧めします。
月経不順(経早)の漢方薬治療
鬱熱タイプ:
このタイプには一般的に「加味逍遙散」を用います。もし陰部の痒みのある人や黄色い帯下が多く出る人は、合わせて「竜胆瀉肝湯」を服用すると効果的です。
実熱タイプ:
本来なら「清化飲」や場合によって「芩連四物湯」を用いますが、日本には製品化されたものがないので、「四物湯」に「黄連解毒湯」を合わせて芩連四物湯の代用とします。この2つを始めから合わせたものに「温清飲」(アトピー性湿疹に汎用されている)がありますのでこれでもいいのですが、熱の状態に合わせて黄連解毒湯の分量を調節できるように、別々のものを合わせて服用する方をお勧めします。服用して冷えすぎるようなら、黄連解毒湯の服用量を2/3または1/2に減らすといいでしょう。もし便秘が強いようであれば、黄連解毒湯の代わりに「大黄牡丹皮湯」を服用します。
陰虚タイプ:
一般に腎陰を補う「六味地黄丸」と肝血を補う「四物湯」を合わせて服用するといいでしょう。もし、生理になるとめまいや頭痛などが起こる人は、六味地黄丸を「杞菊地黄丸」に代えるとより効果的です。
気虚タイプ:
このタイプには「帰脾湯」(「加味帰脾湯」でもよい)か「補中益気湯」を用いますが、経血量が多量で貧血気味になる人は、止血作用のある「田七人参」をこれに合わせて服用するといいでしょう。
月経不順(経遅)の漢方薬治療
肝鬱タイプ:
市販では、本来の「柴胡疏肝散」を用いるのですが、医療用にはないので、処方箋で服用したい場合は、「逍遙散」「抑肝散」あるいは「四逆散」を用います。どちらを選択するかについては、もし手足の冷えが気になる方は四逆散を選択し、胃腸が弱い方は逍遙散や抑肝散を選択するといいでしょう。
寒邪タイプ:
日本の製品の中から選択する場合は「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」を試すといいでしょう。また、下半身は冷えるが、温まりすぎると上半身がのぼせぎみになりやすいという人は、「温経湯」のほうがいいでしょう。
陽虚タイプ:
本来なら右帰飲がよいのですが、日本では製品がありませんので、「牛車腎気丸」あるいは市販で保健薬にはありませんが「海馬補腎丸」を用いるといいでしょう。月経痛を伴う人は、「当帰建中湯」を使ってもよいでしょう。
血虚タイプ:
一般的には「四物湯」を用いますが、胃腸の弱い人は「帰脾湯」や「補中益気湯」を使い、気虚証の症状を伴う人は「十全大補湯」や「人参養栄湯」を使うといいでしょう。
月経不順(経乱)の漢方薬治療
肝鬱タイプ:
このタイプの経乱の人は、経遅と同様に、ストレスを発散して子宮に運ばれる血を調節できる「逍遙散」あるいは「抑肝散」を選択するといいでしょう。もし月経時に気持ち悪くなることがある人は「抑肝散半夏陳皮」にするとよく、のぼせや咽の乾きなどの熱症状を伴う人は「加味逍遙散」にするといいでしょう。
腎虚タイプ:
このタイプの経乱の人には、腎気を補って婦人科系の調節ができる「右帰丸」などがいいのですが、日本にはこの漢方の製剤はありませんので、血を増やして出血も止めることの出来る「芎帰膠艾湯」をベースに、腎を補う「八地味地黄丸」か「六味地黄丸」を合わせて服用するといいでしょう。このとき足腰が冷える人は「八地味地黄丸」を選択し、逆に手足のほてりを感じやすい人は「六味地黄丸」を選択します。
脾虚タイプ:
このタイプの経乱の人は、脾胃の元気を回復して、血の不足や流出を補正できる「帰脾湯」を選択します。もし、ストレスを感じやすい人ならば、「加味帰脾湯」の方がいいでしょう。
不妊症の漢方薬治療
不妊症を漢方薬で治療するには、多かれ少なかれ先天の生命力を高める「補腎薬」(続断・兎絲子・桑寄生・肉蓯容・仙霊脾・杜仲など)が必要となりますが、日本にはこうした生薬が配合されている既製の漢方製剤はあまりありません。下記には、日本の漢方製剤を中心にしたものを紹介しますが、年齢の高い方や複雑な体質の方は、補腎薬を服用できる煎じ薬で個別対応しないとなかなか結果がでないこともご承知おきください。
肝鬱タイプ:
基本的には「逍遙散」(ストレスが熱化している人は「加味逍遙散」)を用いますが、経後期には「杞菊地黄丸」に変更するか、これを一緒に服用します。また、月経痛がひどい人は、行経期に「折衝飲」などの活血剤を併用するといいでしょう。
寒邪タイプ:
既製の漢方製剤の中には、適応するものがあまりありませんが、しいて言えば、通常は「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」を用いて、行経期には「折衝飲」か「桂枝茯苓丸」を併用します。もし透明なおりものが多いタイプの人なら、通常のものを「真武湯」に変更してください。
陽虚タイプ:
経後期には「温経湯」を使って温めながら血を増やし、排卵後の経前期になったら「八味地黄丸」に変更して、腎陽を温めて基礎体温が上昇するようにします。
陰虚タイプ:
「杞菊地黄丸」を使って肝腎の陰血を補いますが、ほてりが強い人は「知柏地黄丸」にします。もし不正出血がある場合は「芎帰膠艾湯」を用います。
血虚タイプ:
「四物湯」を用いるのが一般的ですが、体力が無く気血が両方とも消耗している人は「十全大補湯」、胃腸が弱く栄養吸収が悪い人は「帰脾湯」を使うといいでしょう。
不育症の漢方薬治療
不育症に用いる漢方薬も、不妊症と同様に「補腎薬」(続断・兎絲子・桑寄生・肉蓯容・仙霊脾・杜仲など)が必要となります。下記には、日本の漢方製剤を中心にしたものを紹介しますが、できれば煎じ薬にして見合った補腎薬を配合してもらうようお勧めします。
①陰虚タイプ:
本来は保陰煎が使われますが、日本の製剤の中から選ぶとすると杞菊地黄丸か知柏地黄丸を用います。ただし、手足のほてりや寝汗・微熱・咽の乾燥など虚熱の症状が頻繁にみられるようなら知柏地黄丸にしてください。どちらも漢方専門薬局で中製薬として売られていますが、病院の処方箋で出してもらえるツムラなどのエキス剤の中にはありません。
②脾腎両虚タイプ:
本来は補腎固衝丸が使われます。日本の製剤で代用できるものがあまりありませんが、海馬補腎丸や至宝三鞭丸・参茸補血丸などが使えます。販売しているメーカーが限られているのが難点ですし、体質的に必ず合うとは限りませんので、専門家に相談して必要なら煎じ薬で対応してください。
③気血不足タイプ:
本来は八珍湯に補腎薬を加味したもので対応します。八珍湯は日本の製剤の十全大補湯で代用できますが、補腎薬があまり入っていませんので、こちらも専門家に相談して必要なら煎じ薬で対応してください。
不育症の人が妊娠した場合の漢方薬治療
病証タイプは不育症と一緒ですが、流産の予防を兼ねて「安胎薬」を配合します。この段階では製剤単位で論じるのは無理ですので、専門家に相談してタイプにあった安胎薬を薬草単位で選んでもらってください。
因みに①の陰虚タイプには、安胎作用のある生薬の中から、桑寄生などの陰を補えるものや、黄芩などの熱を抑えるものを選びます。②の脾腎両虚タイプには、安胎作用のある生薬の中から、さらに醒脾作用のある縮砂などと、補腎作用のある兎絲子などを組み合わせて使います。③の気血不足タイプには、安胎作用のある生薬の中から、さらに補気作用のある白朮などと、補血作用のある白芍薬などを組み合わせて使います。
更年期障害の漢方薬治療
日本の漢方薬製剤で、腎陽虚に用いるものには「八味地黄丸」と「牛車腎気丸」があり、腎陰虚に用いるものには「六味地黄丸」があります。とくに病院の処方箋で服用できるものにはこれしかないといっても過言ではなく、したがって更年期障害に用いる漢方薬もこれ以外に選択の余地がありません。そのため、陰陽失調の進行に対応させることもあまりできません。
もし、陰陽失調の進行に対応させたいと考えるなら、漢方専門店で市販されている「中製薬」と呼ばれる丸剤の中からは、いくつか選ぶことができます。
①肝の熱の亢進を伴う人(めまい・耳鳴りがこれによる症状):
六味地黄丸を「杞菊地黄丸」に変更するとより効果的です。
②心の熱の亢進を伴う人(動悸・不眠がこれによる症状):
六味地黄丸を「知柏地黄丸」または「天王補心丹」に変更するとより効果的です。
③脾の冷えを伴う人(食欲不振・むくみ・軟便や下痢がこれによる症状):
八味地黄丸に「人参湯」を加えて服用するとよいでしょう。
④皮膚の乾燥や痒みや蟻走感(皮膚を蟻が這い回るような感覚)を覚える人:
六味地黄丸か杞菊地黄丸に「当帰飲子」を加えて服用するとよいでしょう。
⑤陰陽両虚に進展している人:
もともと、製剤では選択の余地がありませんので、冷えのぼせのうち、もし冷えの方が強い人なら八味地黄丸、のぼせの方を強く感じる人なら六味地黄丸にします。
月経前症候群(経前情緒失調)の漢方薬治療
①気滞タイプ:
通常は「逍遙散」を用いますが、熱化してのぼせやめまい・頭痛などを伴う人は「加味逍遙散」を用います。もし血行が悪く生理痛がひどい場合は「血府逐瘀丸」を用いるといいのですが、市販薬で専門店にしか置いてありませんので、病院の処方箋で飲む場合は「四逆散」と「四物湯」の2種類を合わせて服用します。
②痰火タイプ:
「温胆湯」を用いますが、血行が悪く生理痛がひどい場合は「桂枝茯苓丸」をいっしょに服用するといいでしょう。
③血虚タイプ:
「養心湯」がよいのですが、日本では製品化されていませんので、「甘麦大棗湯」と「四物湯」を合わせて服用するとよいでしょう。
子宮筋腫・卵巣膿腫(癥瘕) の漢方薬治療
日本で子宮筋腫の漢方製剤というと、「桂枝茯苓丸」が最も有名で、なおかつこれが唯一のものです。しかし「貴方の病気のタイプ」で紹介したように、子宮筋腫や卵巣膿腫は大きく気滞・瘀血・痰湿のタイプに分けられますので、本来はそれぞれにあわせたものが必要となります。
桂枝茯苓丸はこれらのうち瘀血タイプに用いるものですが、他のタイプに有効な製剤がないこともあり、病院などでは「馬鹿の一つ覚え」の如くこれを出します。桂枝茯苓丸のナンバーは「25」、同類の桂枝茯苓丸加薏苡仁のナンバーは「125」ですので、これらの番号のものを既に服用されている人は、自分のタイプがマッチしているかどうかを「貴方の病気のタイプ」のカテゴリを参照して、確かめてみるのもいいでしょう。因みに桂枝茯苓丸加薏苡仁は、瘀血に少々痰湿が加わっているタイプに用います。
では、気滞タイプや痰湿タイプの人はどうしたらよいのでしょうか。一番いいのは、専門店に行って煎じ薬でマッチしたものを作ってもらうことをお勧めしますが、煎じ薬が服用できないという方は、次のものを試してみてください。
気滞タイプ:桂枝茯苓丸に九味檳榔湯を加えて、気滞への対応を強化します。
痰湿タイプ:桂枝茯苓丸に二陳湯を加えて、痰湿への対応を強化します。もし湿熱になって黄色い帯下が出ている人ならば、桂枝茯苓丸を大黄牡丹皮湯に変更するといいでしょう。
帯下病の漢方薬治療 {<>は病院で出す漢方の番号、<>がないものは病院にないもの}
①痰湿タイプ:
本来なら「完帯湯」を用いるのですが、日本にはないため「胃苓湯」<115>で代用します。
②湿熱タイプ:
本来なら「易黄湯」を用いるのですが、日本にはないため「黄連五苓散(黄連解毒湯<15>+五苓散<17>)」で代用します。ストレスによる鬱熱が影響してこのタイプになっている人は、「竜胆瀉肝湯」<76>を用います。
③気虚タイプ:
「参苓白朮散」を用いますが、日本では市販薬にしかないので、病院の処方箋で服用する場合は「六君子湯」<43>が使えます。内臓下垂や立ちくらみがある人は「補中益気湯」<41>の方が効果的です。
④陽虚タイプ:
腎の陽虚タイプでは「牛車腎気丸」<107>か「八味地黄丸」<7>を用います。脾の陽虚タイプでは「人参湯」<32>を用い、もし帯下の量が多い人は「五苓散」<17>を合わせて使います。脾腎陽虚タイプの場合は「真武湯」<30>と「人参湯」<32>を合わせて使うといいでしょう。
⑤陰虚タイプ:
「知柏地黄丸」を用いますが、日本では市販薬にしかないので、病院の処方箋で服用する場合は「六味地黄丸」<87>が使えます。
【 記事一覧へ 】