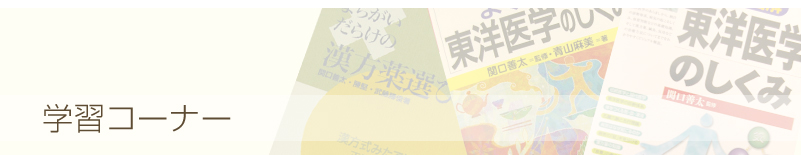学習コーナー
運動器系の鍼灸治療 [鍼灸の知識]
腰痛の鍼灸治療
基本的に、腰痛に用いる処方(ツボの組み合わせ)には、経絡の循行を促して鎮痛をはかるためのものと、証タイプの相違に対応して原因に対処するものとで構成されます。このうち経絡の循行を促すものは、疼痛局部かその付近の経穴(ツボ)と、罹患している経絡の遠隔部にあるもの(「遠位循経選穴」という)を組み合わせます。足太陽膀胱経の遠位循経選穴には「養老」穴、督脈の遠位循経選穴としては「人中」穴、足少陽胆経の遠位循経選穴としては「陽陵泉」穴などがあります。これらの経穴には、実証では瀉法という操作(=手技)を施して経絡の阻滞を除き、虚証では補法を施して患部の回復を促します。
各証タイプに対応した経穴は、次のようになります。
寒湿タイプ:
寒邪を除く経穴か湿邪を除く経穴を用いますが、場合によって両方を組み合わせて(「配穴」という)、これに瀉法を施します。その寒邪を除く経穴の代表は腎兪・命門・関元兪、湿邪を除く経穴の代表は脾兪・陰陵泉です。手技では、冷えが強い場合、局所の経穴も含めて灸頭針や火針といった「温補」を瀉法に加えて施すとより効果的です。
気血阻滞タイプ・瘀血タイプ:
瘀血を除く(「活血」という)経穴を用いるか、さらに気滞を除く(「理気」という)経穴を配穴し、これに瀉法を施します。活血の経穴の代表は三陰交・血海、理気の経穴の代表は間使・内関・太衝です。
腎虚タイプ:
腎の精気を補う経穴に加えて、腎陽虚に偏っている場合は温補に用いる経穴、腎陰虚に偏っている場合は補陰に用いる経穴を用いて、これらに補法を施します。腎陽虚に偏っている場合は灸頭針など温補の作用を強化するとより効果的です。代表的な経穴には腎兪・太谿・復溜・関元などがあります。
病証タイプ | 鎮痛をはかるための経穴 | 証タイプの相違に対応した経穴 |
寒湿タイプ | 疼痛局部かその付近の経穴 + 罹患している経絡の遠隔部にある経穴 | 腎兪・命門・関元兪・脾兪・陰陵泉など |
気血阻滞タイプ 瘀血タイプ | 三陰交・血海・間使・内関・太衝など | |
腎虚タイプ | 腎兪・太谿・復溜・関元など |
膝痛の鍼灸治療
膝痛に用いる経穴の処方(ツボの組み合わせ)は、経絡の循行を促して鎮痛をはかるためのものと、証タイプの相違に対応して原因に対処するものとで構成されます。経絡の循行を促して鎮痛をはかる経穴は、腰痛とは異なって多くは膝周辺のもの「鶴頂」「犢鼻」「内外の膝眼」「委中」などの経穴を用います。このほかにも、経穴図を見て膝周囲の経穴が実際の疼痛部に近ければ、それを選択してもかまいません。
証タイプの相違に対応して原因に対処するものとしては、「異病同治」の考え方から、腰痛で紹介したものを応用できます。異病同治とは、「病名は異なっていても、病証タイプが同じであれば、同様の治療方針で治療できる」というものです。つまり鍼の場合は、多くの同じ経穴が応用されます。
したがって、ここでは腰痛にないタイプのものについて紹介するにとどめます。
湿熱タイプ:
湿邪を除く経穴(陰陵泉など)と熱邪を除く経穴(曲池など)を配穴して、これに瀉法を施します。
気血両虚タイプ:
気の不足を補う「補気」作用のある経穴(気海・足三里など)と、血の不足を補う「養血」作用のある経穴(血海・三陰交など)とを組み合わせて、これに補法を施します。
肝腎不足タイプ:
腎の精を補う「補益腎精」作用のある経穴(太谿・懸鍾など)と、肝血を補う「養補肝血」作用のある経穴(三陰交・肝兪など)とを組み合わせて、これに補法を施します。
※腰痛も膝痛も、軽度の場合、紹介した経穴に自分で按摩やマッサージすることも可能です。しかし一般の人が行うと、早く治したいあまり、やりすぎて返って炎症が強まることがよくあります。毎日少しずつ根気よく行うことをお勧めします。
病証タイプ | 鎮痛をはかるための経穴 | 証タイプの相違に対応した経穴 |
寒湿タイプ | 疼痛局部かその付近の経穴 (鶴頂・犢鼻・膝眼・委中など) | 腰痛の同じタイプを参照 |
瘀血タイプ | ||
湿熱タイプ | 曲池・陰陵泉など | |
気血両虚タイプ | 気海・足三里・血海・三陰交など | |
肝腎不足タイプ | 太谿・懸鍾・三陰交・肝兪など |
【 記事一覧へ 】